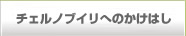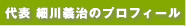水フォーラム
2010-11-23 (火)
22日、国際ビルでの会に出向き、「釣りバカ日誌」でおなじみの中本健氏の講演を聴いた。1970年代、人口増加に追い付かず数%の下水道普及率のせいで洗剤の泡だらけの多摩川が、美濃部都政の元、その普及率を上げたことで毎年少しずつ川が生き返ってきたこと、近所の子供たちが川遊びをするようになったことを、熱い情熱とともに話された。「B級俳優は、弱いもの、目立たないものに共感する」と謙遜しながら、汚染のひどかった時代から、背骨の曲がった雑魚たちを水槽で飼い、その魚たちが子孫を残していく姿に感動しながら応援してきたと言う。子供たちに川の面白さを知ってもらいたくて、紙芝居を作り自演しその仲間を増やしていき、ついには学校の総合学習に採用され、今では、ふつう学校側が嫌がる川での課外授業までをも実施しているという。事故が起きると訴訟になるからと、昔の時代とは違い課外授業の少なくなった都会の子供たちとその保護者そして、先生たちまでもが川を楽しんでいて、学校の下駄箱にはそれぞれの生徒個人のライフジャケットが置かれているのである。現在では下水道普及率は97%まで上がり、都の下水排水基準を0.5ppmまで引き下げて、より一層の川の浄化にまい進しているとのこと。清流にしか棲まないというアユの大量遡上も見られるようになって、川はまさに生き返ったのである。そして、何よりも、誰も寄り付かなかった川が、遊び場となったというとても素晴らしい講演であった。
それに比べると、寄付金を使って様々な活動をしている道内の各団体のビオトープ造成や森作りなどの発表は、ありのままの自然を愛し親しむ中本氏の話の後では、とても色あせていた。消滅しかけている自然を回復させるのはまだ良しとしても、無理矢理になんでも作ることには賛成しかねるものである。
先日4kmほど歩いた落ち葉の自転車道